貴族の本棚 第9回「苦役列車」
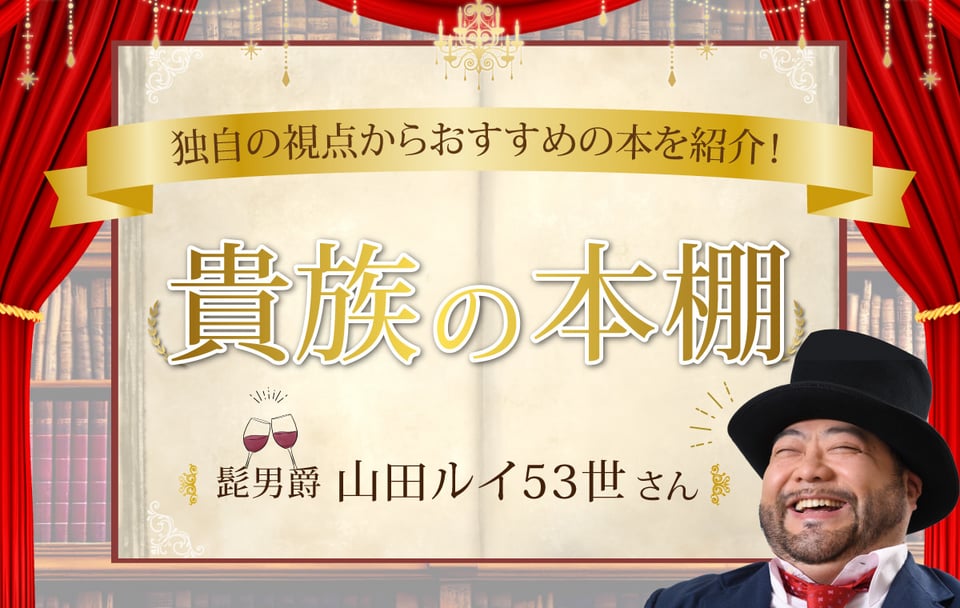
お笑いコンビ「髭男爵」のメンバーである山田ルイ53世さん。ライブ活動やラジオ番組のレギュラー、声優などに加えて、近年では、「ヒキコモリ漂流記」「一発屋芸人列伝」など書籍の執筆、雑誌の人生相談など、独自の文才を生かした執筆活動も注目されています。
第9回目は、「これは自分のことを描いているのでは」と思ったほどに深い共感をもったという作品を教えていただきました。
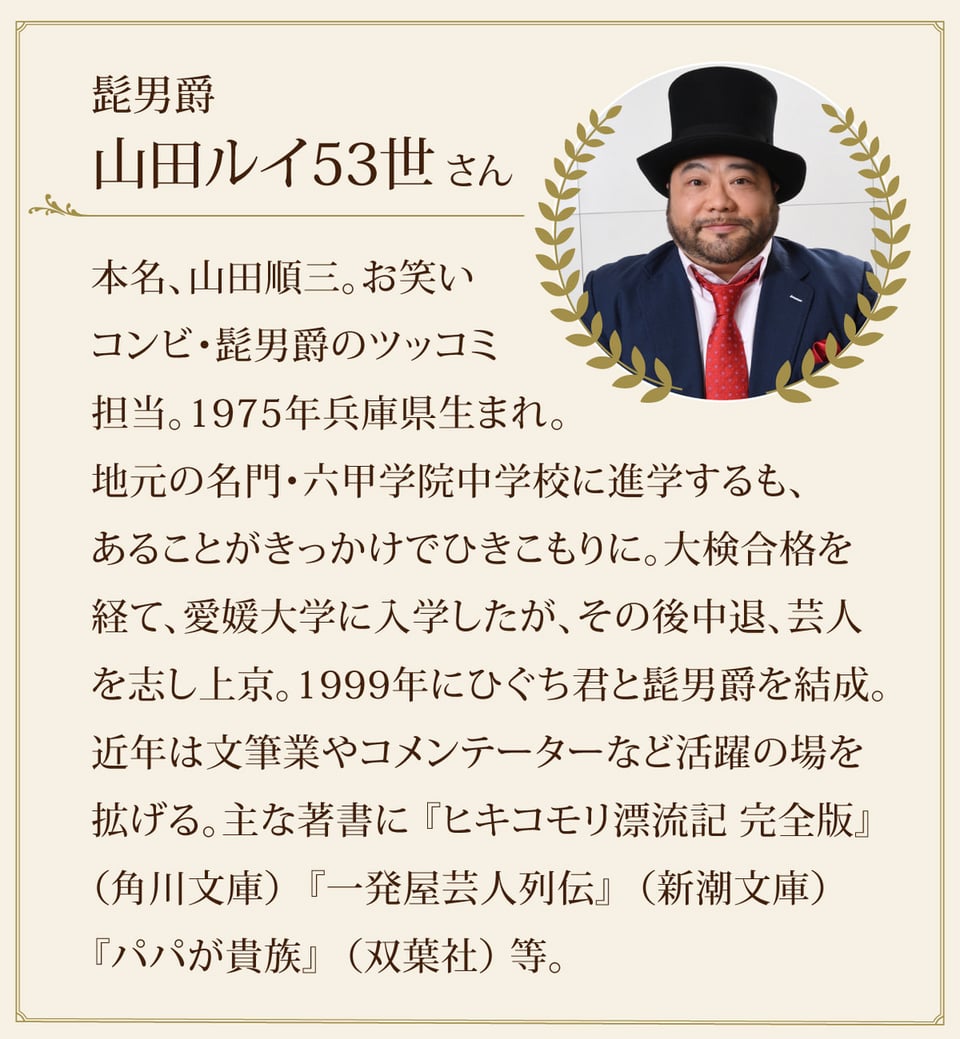
第9回
苦役列車
(著:西村賢太/新潮文庫)
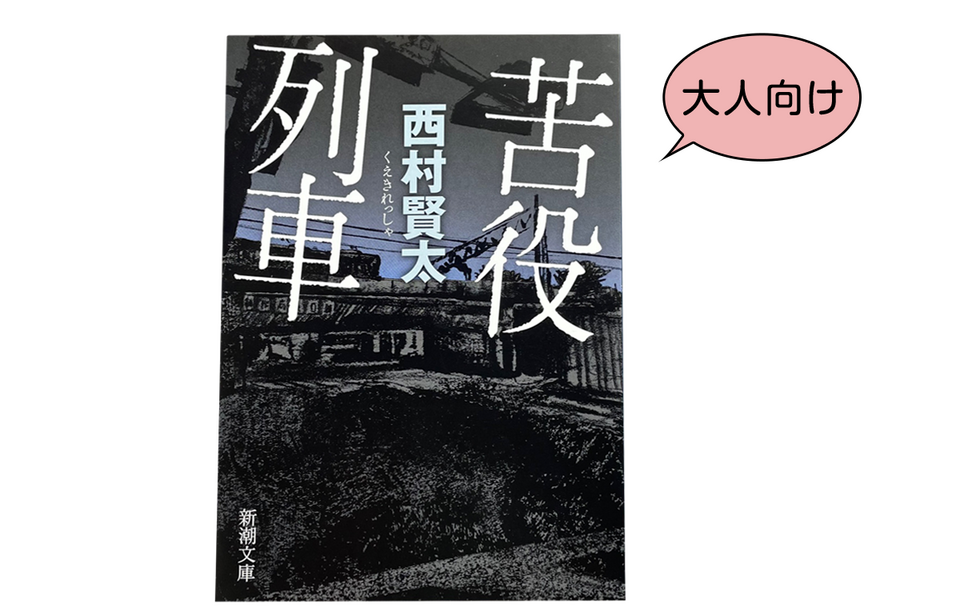
あ、これ、俺自身や。
「苦役列車」のタイトルを見て思った
西村賢太さんが芥川賞を受賞したのは2011年。そのニュースを何気なく見たときに、受賞作のタイトル『苦役列車』が目に飛び込んできました。
そのとき、本当におこがましい話ですが、「これ、俺が乗ってる列車や」と思ったんです。しかも、急行や特急ではなく「各停」だと。
中学校の途中から不登校になり、引きこもり生活を送った後、大検を受けて大学に潜り込んだものの、夜逃げ同然に上京。三畳一間の部屋で十年近く暮らし、お笑いの道へ進まんと正統派漫才を目指したのに、気がついたらシルクハットを被って「一発屋」と呼ばれ……。この道のり自体が「苦役列車」じゃないかと思ったのです。
折しもこの頃、僕は芸人としてブレイクした少し後。「一発屋」という「熱くて苦い球」を飲み込むことを拒否して、後輩におごってみるなど見栄を張っていた時期でした。
主人公の北町貫多は、中卒で家を飛び出し、日雇いで港湾の荷役の仕事をしています。唯一の楽しみが読書で、稼いだ日銭は酒などに使ってしまい、人間関係もうまくいかない。そんな主人公に非常に親近感をもちました。
2021年6月には、西村さんと「人生の日暮れに、生きる意味を知る」というタイトルで対談もさせていただきました。
重たい荷物を抱えた経験のある人は
信用できる
貫多は港湾で重い荷物を抱える仕事をしているのですが、実は僕も「荷揚げ」という、建築現場の指定された場所まで建築資材を運ぶアルバイトをずっとやっていました。
作業は基本的に手作業です。厚さ9ミリの石膏ボードを人力で何百枚も運ぶのですが、これは本当に辛いです。
知っていますか。人間って、重すぎるものをもたされると、泣きそうになるんです。
そのときの後遺症で、僕の腰は、いったん前にかがむと、その姿勢のまま固まってしまいます。
僕は「重い物をもったことのある人は信用できる」という信念をもっています。人は働くとき、なるべく割のいいものを探します。そのためにスキルを身に付けたり、自己研鑽をしたりします。しかし、泣きそうに重たいものを運ぶ仕事を、選ばざるを得なくなることもあります。
重たい物を運ばないと建造物は造れないので、社会のインフラを築く上では大事な仕事です。それを逃げずにかいくぐってきた人は、信用できると僕は思います。
だから、同じような体験をしてきて、それを余すところなく私小説として表現した西村さんを、僕は信用できると思いました。
※私小説(ししょうせつ)とは…作者の身辺の経験や心境などを、作者自身を主人公として書いた小説。
創作では描けない「リアルさ」に
救われることもある
西村さんは対談で、「あとの人生、小説を書くだけ」とおっしゃっていて、そこからおよそ半年後の2022年2月に亡くなられました。そういうところが西村さんらしいなと思います。
私小説は決してハッピーエンドではないジャンルですが、僕は、その感じも味わってほしいなと思っています。全てのエンターテインメントが決して腑に落ちやすい、きれいにまとまったものではない。美談ではないんだということを知ってもらいたいです。
あつらえたもの、きれいに揃ったものしか消費していないと、人間として弱くなるかもしれない。だから、「しんどさ」も知ってほしい。
ただ、それは作品に触れて味わってほしいこと。リアル版「苦役列車」には乗ってほしくないです。
西村さんの、自分のみっともなさ、情けなさをさらけだした文章に救われる人もいるでしょう。世の中は、「前を向こう、上を向いて」と求めてきますが、私小説に触れて「こんな人もいるんだ」と楽になる人もいるはずです。
「だめな人だな」「こんな人がいるんだ」と、お手本にならないけれども現実に存在する人の、弱さやダメさを描いているからこそ面白い。
それが、私小説の良さだと思います。
****
次号でも、山田ルイ53世さんのおすすめの本をご紹介していきます。
お楽しみに!
この記事を読んでのご感想もお待ちしております!ポピーfプラス投稿フォームよりご感想をお寄せください。